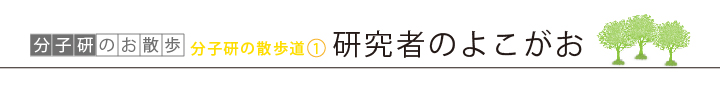
TOPページ > 田中晃二

私たち人類は、太古から生物によって蓄えられてきた、石炭、石油などの化学エネルギー(原子と原子の間の結合によって物質に蓄えられているエネルギー)に依存して文明を築きあげてきました。
しかし現在、エネルギー問題は人類にとって非常に最も重要な問題となっています。田中先生は、エネルギー問題を解決するために化学を役立てたいと考えています。田中先生の専門分野は金属錯体です。錯体というのは、鉄や銅などイオンを中心とし、その周囲に他のイオン・原子・分子などが立体的に規則正しく配置されて生じた分子やイオンなどの原子集団のことをいいます。金属錯体を、触媒(それ自身は変化をしないが、他の物質の化学反応の仲立ちとなって、反応の速度を速めたり遅らせたりする物質)として使うことにより、電気エネルギーと化学エネルギーを相互に変換することを目指して研究しています。
もっと詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
http://www.ims.ac.jp/know/bio/tanaka/tanaka.html
http://sakutai.ims.ac.jp/lab/tanaka-G/
ビデオ:http://www.ims.ac.jp/know/bunshi_video.html
研究者になったのはなぜですか?
高校時代の先生の影響が大きいと思います。「文化や化学産業が進んだといっても、人間はまだ葉っぱ一枚が行っている化学反応もできない」と言われたのをよく覚えています。
それから、子供のころから「どうしてゾウや牛のような大きな動物が枯れ草や草を食べて生きていけるのだろう」ということが不思議でしょうがなかったですね。
最も気に入っている仕事は?
まだありません。
そういうことを考えると、自分の小ささを思い知らされることになるから考えません。私の仕事は、まだまだエネルギーを消費している範囲段階で、エネルギーを作っているという領域に達していませんから。
化学者としての大いなる夢!!
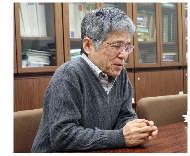 私の最も興味あるところは「生物はなぜ、いとも簡単に各種のエネルギーを作り出せるのか?」というとても素朴なものです。私は金属錯体を触媒とする反応を研究対象としてきましたが、私の興味は触媒ではないんです。さっきもお話ししたように、どうしてゾウや牛のよ うな大きな動物でも草や枯れ草なんかを食べて生きていくための十分なエネルギーを作り出しているのだろう、って不思議に思いませんか?
私の最も興味あるところは「生物はなぜ、いとも簡単に各種のエネルギーを作り出せるのか?」というとても素朴なものです。私は金属錯体を触媒とする反応を研究対象としてきましたが、私の興味は触媒ではないんです。さっきもお話ししたように、どうしてゾウや牛のよ うな大きな動物でも草や枯れ草なんかを食べて生きていくための十分なエネルギーを作り出しているのだろう、って不思議に思いませんか?
私たちのおなかの中で起こっていることを、試験管内でやってみたい、と思っています。こういうことを言うと、“生物は別格だ”という意見がよく聞かれます。でも、生物のまねをするのではなく、同じようなことを別の方法で達成すればいいんです。そのひとつの方法として、銅や鉄などのありふれた金属錯体を触媒として使えれば、と思っています。こちら私は、エネルギーを効率よく得るシステムとして生物を捉えています。
一方、葉っぱが光合成を行っているということについてですが、光のエネルギーを有機物に蓄える(化学エネルギーに変換)という反応で地球上の生命が保たれています。素晴らしいですね。
私の夢の反応ですが、二酸化炭素と水だけを材料として、電気あるいは光などのエネルギーを加えてメタノールを作ることです。そして、メタノールからまた効率よく電気エネルギーとしてを取り出せるようにすることです。
オーストラリアの砂漠全部に800 km x 800 km今の性能の規模で太陽電池を設置すれば日本全体の電力が賄えるという試算があります。でも、オーストラリアの砂漠で作られた電気エネルギーを日本まで運ぶ手段がないんです。この電気エネルギーを使ってメタノールを作ってやればメタノールはエネルギーを蓄えた物質として運べます。
私はほら吹きかもしれませんね(笑)。