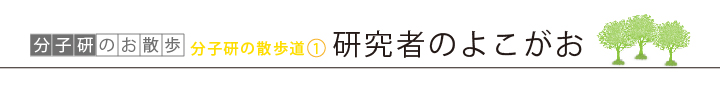
TOPページ > 永田 央
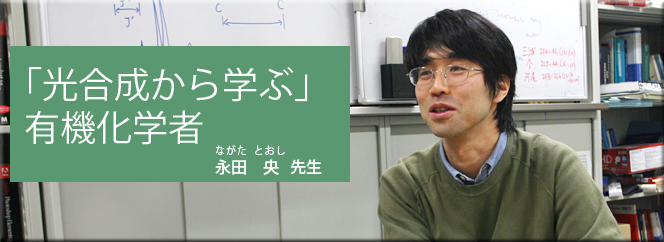
生物の営みはもとをたどれば化学反応に行きつきます。
生命を理解しようという研究は多くなされていますが、その多くは生命から分子レベルの方向(要素を理解する方向)です。その逆方向、言い換えると人工分子を組み立てて生命と同様の働きを実現させようというアプローチはあまりされていません。
もっと詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
http://www.ims.ac.jp/know/material/nagata/nagata.html
研究者になったのはなぜですか?
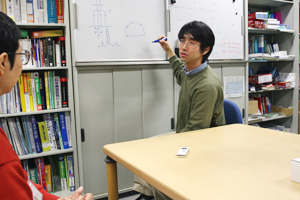 研究者への道を進むかどうかを考えるのは普通、博士課程に進学するかどうかということだと思うんですが、私の場合なぜ博士課程に進学したかわからないんです。修士課程2年生の就職をどうしようか考えていた時、指導教授だった丸山和博先生から「君は博士課程に進みなさい」と言われて進学したので。
研究者への道を進むかどうかを考えるのは普通、博士課程に進学するかどうかということだと思うんですが、私の場合なぜ博士課程に進学したかわからないんです。修士課程2年生の就職をどうしようか考えていた時、指導教授だった丸山和博先生から「君は博士課程に進みなさい」と言われて進学したので。
今の研究テーマ「光合成」との出会いは?
理学部化学科の出身で、卒業研究から博士課程までずっと丸山先生の研究室で有機合成化学をやっていました。この頃から“光合成モデル”が研究テーマでした。ただ、 “エネルギー変換”ということを強く意識するようになったのは分子研に来てからですが。
今のテーマというのは?
人工的に合成した分子を組み合わせて、フラスコ内で、光合成のやっている化学反応を実現させることです。
私の興味の本質は、生命がさりげなく実現している見事な化学エネルギー変換を、フラスコ内で再現させてみたいというものです。きっとそこから何か見えてくるものがあるはずです。
光合成は生体の行っている化学反応の一例です。
光合成を選んだ理由は?
光は外界から入ってくるものです。実験するという立場からいえば、外からコントロールしやすいということです。これが光合成をターゲットとする一つの理由ですね。例えば、今は定常光を当てて実験していますが、将来的にはタイミングをはかって照射してやりたいと思っています。そうすることによって、反応のコントロールにつながるのではないか、という予想があるからです。
もちろん、光合成ができれば光エネルギー変換が可能となりますから、人類の役にも立ちますよね。