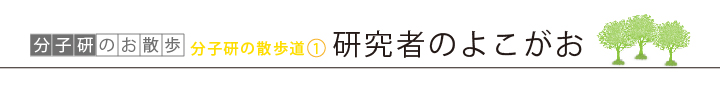
TOPページ > 永田 央
最も気に入っている仕事は?
キノンプールの仕事ですね。2007年の仕事になります。
キノンプールというは?
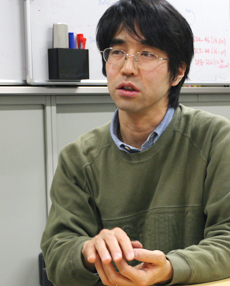 光合成というのは、太陽エネルギーを使って有機物を作るわけです。このとき、実は太陽エネルギーを1回使うだけでは足りないんです。2回に分けて使わないといけない。太陽エネルギーを2回使って初めて、二酸化炭素から有機物を作るだけのパワーが得られるわけです。そこで、太陽エネルギーを2回に分けて使う間に、1回目のエネルギーをためておく仕掛けが必要になります。それがキノンプールです。キノンという物質がたくさん埋め込まれたものです
(詳細はhttp://licht.ims.ac.jp/subject/index.htmlの項目1をご覧ください)。
光合成というのは、太陽エネルギーを使って有機物を作るわけです。このとき、実は太陽エネルギーを1回使うだけでは足りないんです。2回に分けて使わないといけない。太陽エネルギーを2回使って初めて、二酸化炭素から有機物を作るだけのパワーが得られるわけです。そこで、太陽エネルギーを2回に分けて使う間に、1回目のエネルギーをためておく仕掛けが必要になります。それがキノンプールです。キノンという物質がたくさん埋め込まれたものです
(詳細はhttp://licht.ims.ac.jp/subject/index.htmlの項目1をご覧ください)。
化学反応としては、キノンという物質が光反応によりキノールという物質に変わります。
このキノンからキノールへの変化を核磁気共鳴(NMR)という手法を使ってはっきりと見ることができました。
そして、3層からできたキノンの層は、NMRで識別できるのですが、中心から進むと思っていたのですが、どの層でも同時に進んでいることを発見しました。
この発見は有機化学関係の人だけでなく、生物関係の人からもとても面白いと評価されました。化学的な面白さというより、生物システムに近い面白さがあるのかもしれません。
研究スタイルの特徴は?
複雑な有機分子、大きな有機分子を使うことですね。
単純な分子は原子の結合する距離の範囲がかなり限定されてしまいます。
そうすると、分子の形に自由度がなくなるため、細かい反応性のコントロールをすることができなくなるんです。だから、自由度を持たせるためには複雑な分子であることが欠かせないんです。
先ほど見せていただいたキノンプールも複雑で大きかったですね。
ええ。あれも、カタログに載っているような市販の物質から20段階以上の反応を経て合成したものですよ。1つの物質を作るのにだいたい半年から1年かかります。
やはり有機合成のテクニックが重要なんでしょうね?
私の研究室では、1つ1つの反応は簡単な反応を使っています。だから、有機合成のテクニックというより、多段反応のテクニックというか、段取りが重要ですね。次の反応を考えながら段取りを組まないと大変です。
そうそう。丸山研究室の出身者はみんなこの段取りの組み方を仕込まれています。企業に就職した人たちから、「研究室で学んだ中で一番役に立っていることは、段取りを考えて仕事をするという点だ」という話を聞きますよ。教育的だと思うんですよ(笑)。