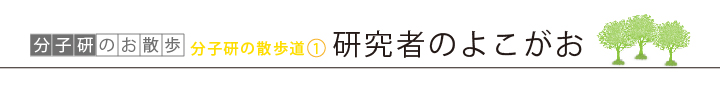
TOPページ > 信定 克幸
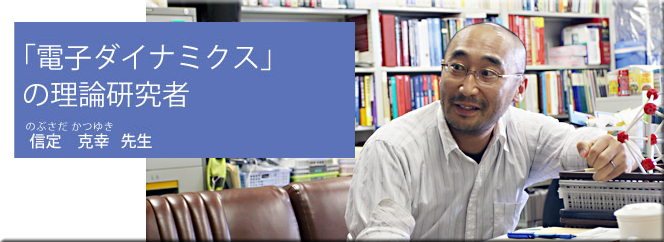
物質を作っているのは原子や分子です。物質への着目のしかたの一つとして、全体の系の中で原子や分子の存在形態をどのように捉えるのかが考えられます。原子や分子が完全に孤立して存在し、周りとの相互作用が全くない場合と、固体のように原子や分子が特定の周期構造を取って凝縮している場合がその両極端になります。ある一面での見方に過ぎませんが、ナノ構造体というのはこの中間的な位置に属し、広い意味での界面、表面など境界のある物質などがその一例です。
先生は、比較的小さな分子が周りと相互作用することにより、界面上あるいは境界といった端のところでどのようなことが起こっているか、またその現象がどのような機能性と関係があるのかということを、電子の動き(電子ダイナミクス)の観点から理解するため、理論的な研究を行っています。
もっと詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
https://www.ims.ac.jp/research/group/nobusada/
http://raphael.ims.ac.jp/research.html
研究者になったのはなぜですか?
小さい頃からモノ作りが好きでしたね。子供なりに、将来は理系に関係することをやりたいと思っていました。
特に、高校生の頃、基礎学問をやりたいと思うようになりました。
そして、大学へ入って、ファインマン先生や朝永先生のような偉大な研究者の業績を次第に知るにつれて、研究者になりたいと思うようになりました。
理論を選んだのは?
 モノ作りが好きでしたから、初めは実験家になりたいと思っていたんですよ。
モノ作りが好きでしたから、初めは実験家になりたいと思っていたんですよ。
もっと正確にいえば、理論ができる実験家になりたかったのです。
大学では理学部でしたが、卒業研究では研究というほどのことはやりませんでした。もっぱら基礎的な勉強をしました。実は、学部を卒業した後すぐに大学院へは行かず、1年間、理論と実験の二足のわらじをはいて研究生として過ごしたんです。この頃、様々な学術書を読みながら、名立たる理論家が確立して来た物理の世界に憧れ、少し幼稚な表現ですが紙と鉛筆の世界がすごくかっこいいと思いました。
それで、翌年大学院に進む際には、二足のわらじを止めて理論の研究室を選びました。
紙と鉛筆の世界に入られてどうでしたか?
醍醐味を感じはしましたが、同時に、自分の力量では紙と鉛筆だけでは到底無理であることもわかりました。
その後、何年も七転八倒して紙と鉛筆のみでは無く、計算機シミュレーションも併用するということに新たな面白さを見出しました。シミュレーションは実験の代わりに計算機を使って確かめる、いわば疑似実験です。“理論のわかる実験家”になりたいという私の従来の希望に一歩近づくことができたわけです。