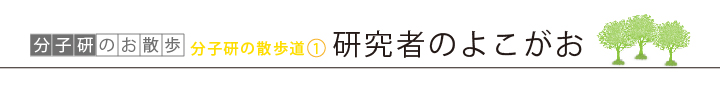
TOPページ > 唯 美津木
今後の研究は?
 化学の研究は、長い目で見ればやはり一般に使われるようになることはとても大事だと思うんです。そのために、基礎的な研究は非常に大事ですし、基礎的な研究でわかったことを積み上げて、何年もかかって社会に還元できるようになります。触媒の場合には、それには一般に10年から20年がかかります。私は、大学や研究所での研究は、そういった研究の芽を出すための種まきのような研究が大事だと思っています。それを育てて実用化する研究は企業が得意としています。これからは、また新しい触媒を作るための方法や触媒を分子のレベルで理解するための研究を行っていきたいと思っています。
化学の研究は、長い目で見ればやはり一般に使われるようになることはとても大事だと思うんです。そのために、基礎的な研究は非常に大事ですし、基礎的な研究でわかったことを積み上げて、何年もかかって社会に還元できるようになります。触媒の場合には、それには一般に10年から20年がかかります。私は、大学や研究所での研究は、そういった研究の芽を出すための種まきのような研究が大事だと思っています。それを育てて実用化する研究は企業が得意としています。これからは、また新しい触媒を作るための方法や触媒を分子のレベルで理解するための研究を行っていきたいと思っています。
こういった基礎的な研究は、すぐに社会での実用に繋がるわけではありませんが、実用化する上で抱える様々な問題を解決し、また新しい触媒を開発するアイディアを与える上で、とても大事なものと思っています。
研究スタイルの特徴は?
私はどちらかというとパソコン上で解析をしたり、計算をしたりというよりは、自分で手を動かして実際に手に取れるレベルで新しい物質を作るのが好きでしたから、卒業研究では合成を強く希望してやらせて頂きました。物理化学の研究室でしたから、先輩の殆どは新しい測定法の開発や分光計測をしていました。合成をされている先輩は1人しかおらず、合成器具も殆どない状態でしたが、毎朝7時頃大学に行って、わくわくしながら実験をしていました。
助手になってからは、自分の研究だけでなく、学生を含めて研究室全体のテーマを指導することが必要になり、時間分解計測のような分光法を主体とした研究にも積極的に携わるようになりました。ですから、“モノを作ること”ができること、“測定法の開発や分光計測”ができること、この両方が出来るのが特徴だと思います。最初は大変でしたが、今にして思うと、研究の幅を広げ、いろいろな角度から触媒のことを理解する上で、大変有益だったと思っています。