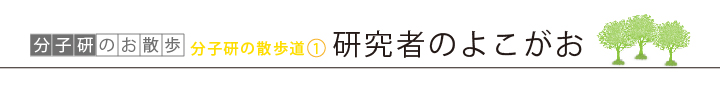
TOPページ > 加藤 晃一
 研究を進展させた決め手は何ですか?
研究を進展させた決め手は何ですか?
名古屋市立大学の高橋禮子先生(現:同大学名誉教授)が糖鎖の配列を決める方法を確立されていました。その方法を取り入れて、糖鎖をもつタンパク質の構造解析が可能となりました。
さらに、高橋先生と共に研究を進め、糖鎖データベース “GALAXY”を作成し、WEBで公開しています(http://www.glycoanalysis.info/galaxy2/)。
今では、X線構造解析などの手法とも組み合わせることにより、糖タンパク質の構造解析、機能解析に関して、世界でもトップクラスの研究チームを作り上げています。
糖鎖研究の現状は?
私が研究を始めた頃は、分子構造が多様でなおかつ不均一であるなどの問題から、糖タンパク質はNMRを使った研究対象としては適していませんでした。ですから結果も出ませんでしたし、また、糖鎖の重要性も今ほどは認識されていませんでした。地味な存在でした。
でも、20年たった今は糖鎖を取り巻く現状が全く変わりましたね。
生命現象における糖鎖の重要性が非常に注目されています。
そして、私が学生時代に研究してきた糖タンパク質としての免疫グロブリンは、今では抗体医薬として医薬品業界の中で主流のターゲットとなっています。
今、最もホットな興味は?
生物はなぜ、糖鎖を使うようになったのか?ということです。
タンパク質に機能をもたせる方法として、アミノ酸だけでできたタンパク質で済ませてしまってもよかったはずです。
これを解き明かすことができれば面白いと思いますね。