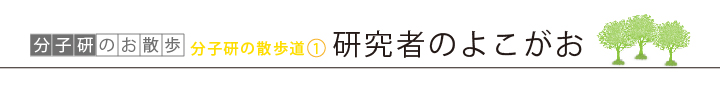
TOPページ > 加藤 晃一

生物の体で使われているタンパク質の多くは、単にアミノ酸がつながっただけではなく、多くの場合は糖がつながった“糖鎖”によって修飾されています。この糖鎖の構造を調べることはとても難しい技術ですが、分子研にはこのような糖鎖の構造を調べるのに適した大型装置があります。それが、920MHz核磁気共鳴装置(NMR)です。
先生は、NMRや他の手法を組み合わせて世界でトップクラスの技術を確立させ、糖鎖の付いたタンパク質の構造を研究しています。
もっと詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
https://www.ims.ac.jp/research/group/katok/
http://www.phar.nagoya-cu.ac.jp/hp/sbk/
ビデオ:http://www.ims.ac.jp/public/vlibrary.html
マメ情報:
糖鎖なんて興味ない、という方へ。
血液型のABOを決めているものは何だと思いますか?これは赤血球上の糖脂質の“糖鎖の構造の違い”によるものです(http://glyence.com/tousa.html参照)。
研究者になったのはなぜですか?
残念ながらドラマティックな動機というのはないんですよ。
大学院に進んで、熱中して研究して、気がついたら研究者になっていた。
面白くないでしょ(笑)。
今の研究テーマ「糖鎖の構造生物学」との出会いは?
 私は薬学部の出身で、大学院の博士課程の頃には、抗体の研究、具体的にはNMRを使って免疫グロブリンの構造を研究していました。その頃から、糖鎖のことがわからないと、抗体の構造や機能がきちんと理解できないことが明らかでした。
私は薬学部の出身で、大学院の博士課程の頃には、抗体の研究、具体的にはNMRを使って免疫グロブリンの構造を研究していました。その頃から、糖鎖のことがわからないと、抗体の構造や機能がきちんと理解できないことが明らかでした。
でも、糖鎖を調べるということはとても大変なことだったので、みんな後回しにしていたんです。それでもやっぱり避けて通ることができませんでした。
それでは糖鎖構造の解析方法から研究を始めたのですか?
そうですね。その当時、安定同位体(放射線を出さず、自発的には他の核種に変化しない同位体)を使ってタンパク質に目印を付けてタンパク質の構造を調べる方法が取り入れられるようになっていました。
私は、この方法を糖鎖に応用しました。
まず、安定同位体で目印を付けた糖を、有機化学的に合成します。そして最終的には細胞に遺伝子を取り込んでタンパク質を合成させます。そうすると、目印の付いた糖鎖をもつタンパク質ができるのです。そして、NMRを使って構造を調べる、ということをしました。
つまり、有機合成から細胞生物学まで、必要な手法はあらゆることを使って実験しました。
しかし、糖鎖の配列というのは、非常に多様性に富んでいて、とても難しいんです。