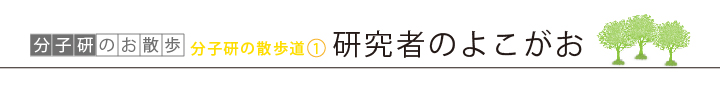
TOPページ > 岡本 裕巳

一般の光学顕微鏡では、光の波長より小さなモノを見ることができません。近接場光学顕微鏡は、そんな光の波長の限界を超えて、小さなモノを見ることができる光学顕微鏡です(詳しくは、http://groups.ims.ac.jp/organization/okamoto_g/beginer/nyumon.html)。
先生は、近接場光学顕微鏡とパルスレーザーとを組み合わせて、ナノサイズの物質について、10兆分の1秒単位の短時間内に起きる変化を調べることに成功しました。今もさらに近接場光学顕微鏡を進歩させています。
もっと詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
https://www.ims.ac.jp/research/group/okamoto/
ビデオ:http://www.ims.ac.jp/public/vlibrary.html
研究者になったのはなぜですか?
 化学に興味をもつようになったきっかけは、小学校の時ですね。担任の先生が、おそらく理科の専門の先生だったのだと思いますが、“H2SO4”とだけ書いてある瓶をもってきて、「これが硫酸だ」と言ったんですね。物質が記号で表される、ということに感動しましたね。反応も記号で書けることに「へぇー!」と感心した記憶があります。
化学に興味をもつようになったきっかけは、小学校の時ですね。担任の先生が、おそらく理科の専門の先生だったのだと思いますが、“H2SO4”とだけ書いてある瓶をもってきて、「これが硫酸だ」と言ったんですね。物質が記号で表される、ということに感動しましたね。反応も記号で書けることに「へぇー!」と感心した記憶があります。
では、最初は“反応”から化学に興味をもったのですね。 先生の研究は分光学(光のスペクトルを研究する学問)から始まっているのですが、分光学との出会いは?
これはかなり明確ですね。私の通っていた高校には赤外分光器があったんですよ。これが大きかったと思いますね。
高校でそのような装置があるというのは珍しいですね?
ええ。教育大学の附属高校だったので、試験校としての導入という意味合いがあったのでしょうね。その後、紫外の分光器も入りました。
化学に興味があったので、毎日のように準備室に出入りして、それを使って遊んでいました。
では、現在のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)の走りのようなものだったのですね!